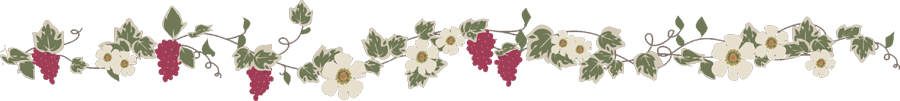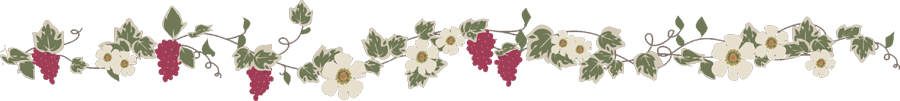
|
■ハロウィン■サリエル×ゼルクVer 「ゼルクー!! 見てこれ!」 教室で、ネルが俺へと見せてくれたのはキラキラと輝く飴玉。 ネルはホント、飴が好きだな。 俺も好きだけど。 「どうしたの、それ」 「いいでしょ。今日はね、ハロウィンだからサリエルがくれるよ」 「ハロウィン? なんだっけ、それ」 聞いたことあるようなないような。 「お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ、って言うとお菓子が貰える日だよ」 「まったくわかんねーけど、そのお菓子くれる係がサリエルってこと?」 「そうそう。あとでゼルクも貰いなよー」 1つしか無いのか、ネルが俺に分けてくれる様子はない。 サリエルは、他の生徒と話してるみたいだし……放課後、声かけてみるか。 それにしても『お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ』なんて、ネルはともかく俺はそんなぶりっこみたいな口調、なんだか恥ずかしい。 言いたいことさえ伝えられればいいんだろうけど。 いたずらされたくなければ、お菓子を寄こせとか? ……うん、それがいいな。 そんなことを考えてたら、授業内容なんてまったく頭に入って来なかった。 「……あれ、ネル。サリエルは?」 放課後、ノートを鞄にしまい教室を見渡すがサリエルの姿が見当たらない。 「もう帰っちゃったのかな。早いね。お菓子取られたくないのかな」 「まあ、どうせ森あたりにいるんだろ。行ってくる」 「大丈夫? ついてこうか?」 「まだ明るいし。奥までは入らないから大丈夫」 そう言い残し、俺は教室を後にする。 いつもならうっとおしいくらいに声かけてくるくせに、今日に限ってサリエルのやつ、すぐ消えやがって。 俺から逃げてんのか? そんなことを疑いたくもなる。 けれど、森の入り口ですぐさまサリエルの後ろ姿を見つけることが出来た。 「サリエル!」 「……ああ、ゼルク。なんだ。1人で散歩か?」 そうだ。 どうせ散歩するならクーシーのこと連れてこればよかったな。 「うん……。あのさ、お菓子……じゃなかった。えっと、俺にいたずらされたくなければ、お菓子寄こせよ」 そう手を差しだすと、サリエルは一瞬きょとんとした顔をするがすぐさま、口元に手を当て軽く笑う。 「なんだ、それ。なんでそんな上から目線なんだよ」 「あ、それは……」 お菓子くれなきゃいたずらしちゃう、なんて言えるかバカ。 意味は一緒だからいいじゃんか。 「別に、上から言ってるつもりはねーよ」 「あっそ」 そう言って、サリエルは俺へと体を寄せる。 つい一歩後ずさりすると、後ろの木へと背中がぶつかった。 「じゃ、どうぞ。いたずらしろよ」 「へ……」 サリエルは、キスでもするつもりかってくらいに俺へとさらに体を寄せ、俺の頬を撫でる。 待て。 この展開は想定外だ。 「……いたずらしていいの?」 「いいぜ」 「えー……」 いざいたずらしていいって言われると、どういうことをすればいいのかまったく浮かばない。 なんだ、俺っていい奴だな。 どうしようか。 っつーか、俺はお菓子が欲しいわけで、いたずらしたいわけじゃない。 つい首を捻っていると、耳元へと顔を寄せたサリエルが小さく笑った。 「ゼルクがしないなら、俺がする」 「は? なんだよ、それ」 「いたずらされたくねーなら、お菓子寄こせ」 「持ってないし、お菓子なんて」 「じゃ、いたずらするぜ」 「ふざけんなよ。なんだよ、その理不尽なの」 「どっちがだ。元々ゼルクが言い出したんだろ。お菓子かいたずらかって」 ……そうだ。 俺ってすっげー理不尽なこと言ってたんだな。 お菓子だなんてかわいいもんだけど、やってることは恐喝じゃないか。 苛められたくなきゃ、菓子出せ! みたいな。 どうしてこうなった? ……そうだ、俺がぶりっこ出来ないせいでこうなったんだ。 意味は一緒なはずなのに。 「いいよな、ゼルク」 「いや、待ってって」 そう俺が言ったにも関わらず、お腹辺りに違和感を覚える。 目を向けると、俺の左の脇腹付近にサリエルの長剣が突き刺さっていた。 「ひぃっ……ぁああっ!!」 「ひぃって、なんだよ、それ」 いや、笑いごとじゃねーし。 サリエルが笑って体を揺らすたびジワジワと服が血で濡れていく。 「うゎあ……マジでやめろって。抜けって! バカ。痛ぇ」 「痛くねぇだろ。そこんとこ、俺は優しいからな」 ……確かに、違和感はあるものの痛くはなくて、サリエルが痛覚を麻痺させてくれているのは理解出来る。 痛覚麻痺はともかく、こんだけ深く刺されたら俺、自分で治せるかどうか……。 時間かかるよな。 というか麻痺と治癒同時にって、難しいし。 下手に動くと傷口広がりそうだし。 「ああもう、とりあえず抜けって。治癒出来ねーだろ」 「待てって。ほら……すげぇ、ぐちゅぐちゅ音してんだけど」 「マジで、掻き回すなって……。気持ち悪ぃ……っ」 「エロくてムラムラしてきた……」 「ふざけんな……っ」 「……森で翼出してんじゃねぇよ」 ああ、俺、翼出しちゃってた? でも、こんなことされてたらそっちになかなか気が回らない。 「なあ……ゼルク。菓子やるからいたずらさせろよ」 「もうしてるだろ」 「そうだなぁ。でもそれなら理不尽でもなんでもねぇだろ? ちゃんとした取引だ」 サリエルの言うとおりかもしれない。 『いたずらされたくなければ菓子を寄こせ』や『お菓子をくれなきゃいたずらしちゃう』なんてのは理不尽な言い分だ。 ……でも待てよ。 今日はハロウィンだから、それが許される日なんじゃないのか? 「……サリエル。今日なんの日か知ってる?」 「……ハロウィンとでも言う気か」 「そう、それ」 「で? 結局、お前は俺にくれる菓子は無いんだろ?」 「……うん」 「じゃあ、俺はゼルクにいたずらする正当な理由があるわけだ」 「なんでっ。サリエルはお菓子くれる係だろ」 「勝手に変な係に任命すんな。っつーか、お前も俺にいたずらすりゃいいっつってんだろ」 「だからぁ。いたずらとか思いつかねーしっ」 そこまで言うと、そろそろ飽きたのかサリエルがゆっくりと剣を引き抜いてくれる。 抜けきったところで、いままで止められていた血がたくさん溢れ出て来た。 「ひぁ……あっ」 「ああ、服脱がせてから切るべきだったな」 「どうでもいい……」 こんなに血が……。 見てるだけで怖くて涙が溢れてくる。 「ゃだ……これっ……あ、止まんない……」 「すげぇ、たくさん溢れてんな。傷口に指突っ込んでいい?」 「やだ……」 「じゃ、俺のちんこ突っ込んでいい?」 「もっとやだよっ!」 「ははっ、やだとか言われるとマジで興奮するし。なあ?」 切れた服の隙間から入りこんだ指先で傷口を撫でられ、体が跳ね上がる。 「やっ……ぁっ」 「な。たっぷり濡れて、こんなに溢れさせて。ぐっちゃぐちゃに掻き回したらたまんないだろうなぁ」 「っ……やっ」 目を瞑ると、涙が頬を伝う。 その涙を拭うよう舌の這う感触がした。 「……この泣き虫が」 「っ……」 からかうようなサリエルの口調。 目を開けると、サリエルは笑みを見せ、俺の頬を撫でていた。 「ガチで怖がってんじゃねぇよ。ほら、治してやった」 見下ろすと、傷口も服が切れた様子も見当たらない。 ただ、俺の服は血で濡れたまま。 「……汚れた」 「お望みなら、俺が洗濯してやるからいますぐ脱げ」 「……やだよ。もういい。自分でする」 「もう暗いから、翼しまえよ」 ……ああもう、なんかサリエルの思うツボだ。 最悪。 帰ろう。 そう背を向けると、腕を取られ引き止められる。 「なんだよ」 「菓子やるって」 「……そういう気分じゃない」 「怒んなよ。ゼルクが言い出したんだろ。菓子寄こせって。俺は同じこと言い返しただけだし。ゼルクは持って無かったから、いたずらした」 「……ふん」 「でもって、お前は俺にいたずら出来ねぇみたいだし? だから菓子をやるのは当然だ」 全部、サリエルの言う通りだからむかつくんだよな。 ため息をつく俺の腕をさらに引き寄せると、口の中になにかをほうり込まれる。 「んぅ……」 甘い。 飴だ。 つい顔が綻びてしまいそうになるのをなんとかぐっとこらえる。 「おいしいだろ」 「っ……おいしいけど、それは別にサリエルのおかげじゃないし」 「はいはい。よかったな、菓子が貰えて」 まったく子供扱いだ。 むかつく。 「これもやるよ」 そう言うと、俺の手にもう1つお菓子を握らせてくれる。 見たことのないお菓子だ。 クッキーか? 「それはクーシーにだ」 「……魔物用のお菓子なの?」 「ゼルクが食べても構わねーけど、魔物でも食べれる」 クーシーのお菓子。 ……クーシーの喜ぶ顔が目に浮かぶ。 ……なんだよ、もう。 これじゃサリエルのこと嫌いになり切れねーし。 ホント、むかつく。 「じゃあ、帰るか」 「……うん」 まだ、溶けきっていない飴を舌で転がす。 甘い。 ……ここでサリエルのこと許しちゃうのは甘いかなぁ。 なんて思うけど、サリエルは絶妙に一線を越えないでいてくれる。 嫌いになれないし、絶対に嫌だと思う一歩手前でやめてくれる。 「もう1個やるよ。こっちは持ち帰り用な」 そう言って、追い打ちをかけるよう、まだ包まれたままの飴を俺に渡してくれる。 「あり……がと」 「気が向いたらまたやるよ」 「……うん」 |