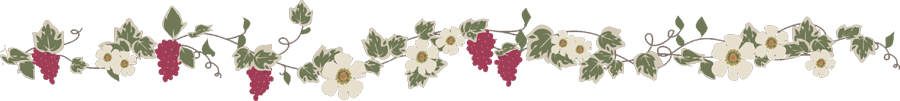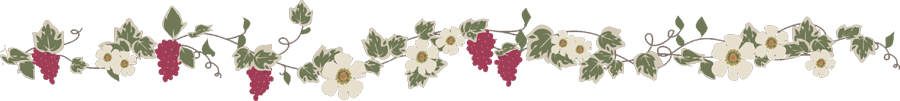
|
■症状D■ 赤。 目の前が、真っ赤に染まる。 辺りは暗いのに、なぜだろう。 なんで、赤くなるんだ? そうか。 君の輝くように真っ白で大きな翼が、この暗さを掻き消してくれていたのか。 俺の視界を埋め尽くす白。 その白が赤く、染まっていく。 俺の視界を、白から赤へと埋め尽くしていく。 俺は羨ましかった。 真っ白な君の翼が。 誰よりも大きな翼。 君は、ときどき俺に触らせてくれた。 柔らかくて、ふわふわしていて。 俺が撫でると、君はいつも気持ち良さそうに目を細めていた。 代わりに君は俺の羽を撫でてくれた。 俺の羽は黒くて、ただの膜で、きっと、つまらないだろうに。 それでも君は、素敵な羽だと褒めてくれた。 俺はそれがお世辞だと、解っていたけれど構わなかった。 何度も何度も、互いの翼と羽を撫で合った。 「うわぁああああっ!!」 一瞬の出来事だった。 状況が把握出来た瞬間、俺は背を向け逃げ出した。 君の赤く染まっていく翼から目を逸らした。 現実から、目を背けた。 助けなければいけないのに、叫ぶことと逃げることしか、いまの俺には出来なかった。 森から外へと抜け出した所で、足がもつれ地面に倒れ込む。 「ぁ……ぅあっ!」 息苦しい。 這いつくばったまま、森へと体を向けるが、暗くてよく見えなかった。 「おい、なにやってんだ」 通りかかった教師に肩を揺すられても、なにも答えられない。 「お前はそいつを頼む。俺は森の中を見てくる」 「わかった」 1人の教師が森へと向かおうとするのが解かり、なんとか必死でその足を掴んだ。 「……俺も、行きますっ」 「お前は残ってなさい」 「俺も……っ」 無理矢理引きはがすようもう1人の先生に抱きかかえられ、俺は部屋へと連れられた。 「ひっくっ……んっ」 「泣いてちゃわからないぞ。なにがあった? 恐い魔物でも見たか?」 「……俺、森にっ」 「ダメだ。この時間帯は危ないって解かっているだろう? なにしに行くんだ」 「友達が、中にいるんですっ」 「まともに歩けないお前が行った所で無駄だ」 「っ……それでも……行かないと……っ」 泣きじゃくる俺に観念するよう、先生は俺の体を抱え外へと出てくれた。 だが森の入り口が見えるところまで近づくと、先生は足を止めてしまう。 すとんと、体を地面へと下ろしてくれるが、手は放してくれなかった。 目を向けた先には、さきほど中へと入っていった教師と、俺の友達。 友達は、教師に抱かれるように横たわり、真っ赤な翼を広げていた。 ……いや、広げてなどいない。 広げるほどの質量はもうそこには存在しなかった。 以前の半分……三分の一ほどになった羽の塊が背中に張り付いて、細く長く伸びる骨組が、元々の翼の大きさを物語っていた。 「っ……はぁっ……ひっ……っ」 「戻ろう。彼も無事、森から出て来たようだし」 「無事……っ?」 「お前がいても、なにも出来ないだろう?」 「はぁっ……」 また、息苦しくなる俺の体を抱きかかえ、遠ざけられる。 俺はその教師を強引に跳ねのけ森の中へと走った。 少し前に見た、真っ赤な視界の場所へ。 「あっ……ぁあっ」 たくさんの染みが広がる地面へと、這いつくばる。 傍には麻酔銃を撃ち込まれたらしい大きな魔物が寝息を立てていた。 俺の大好きな、君の翼。 その一部が、残骸のように散らばっている。 掻き集めてみても、赤くて湿ったその塊は、両手で包めてしまうほどの量しかない。 それを狙うよう、他の魔物が俺の周りを取り囲んだ。 「っ……やめろよぉ……っ。これ以上、ラグエルの羽を食べるなっ!」 両手で包み込み、お腹に抱え、赤い塊を守る。 魔物に肩を突かれても、体を転がされてもこれだけは、渡すわけにはいかない。 「俺の……っ、俺のを食べろよぉ……っ」 痛い。 体も心も痛くて気持ち悪い。 「ああもう、なにやってんだ!」 追いかけて来た教師が、また俺の体を抱き上げる。 俺は、拾い集めた赤い塊を落とさないよう必死で身をかがめた。 「うっ……俺も……俺も、食べられたぃ……っ」 「バカなことを言うな。1人でも助かったことを、幸せに思え」 「思えるもんかっ。俺だけ助かるだなんて、不幸だっ」 「だいたい、お前の羽と彼の翼は別物だ。お前の羽が食べられることはない」 「なんでだよぉ……。なんで違うんだよ……っ。先生……。俺の羽、壊して……っ」 「そんなことはしない」 「じゃあ、自分でやるっ」 「それで、彼が報われるとでも思ってんのか」 ああ、きっと報われない。 けれど、このままでは俺の心だって報われない。 ……そうか。 俺はただ自分が苦しくて、それから逃げたくて、自分を傷つけたいだけなんだ。 自分を傷つけることで、罪悪感から逃れたいだけなんだ。 「いいか。ちゃんと部屋で休んでるんだぞ。ちょこちょこ監視してるからな」 部屋のベッドに寝転がらされ、1人にされる。 俺は眠ることも出来ず、ただ真っ赤に染まった手を眺めた。 『君が自ら羽を壊しても、僕は嬉しくないよ』 君ならそう言ってくれるのかもしれない。 俺は、自分の背に黒い羽を広げるが、傷付けることが出来なかった。 この羽は君が以前、褒めてくれた羽だから。 いっそ、君の手で壊してくれないか。 こんな真っ黒な羽を、君は素敵だと言ってくれた。 君が褒めてくれたから、いつしかこの羽は俺の自慢になった。 持ち帰った赤い塊に水をかけてみるが、元の白には戻ってくれない。 それでも乾燥すると、ほんのり赤みを帯びた羽たちはふわふわと宙を舞った。 まぎれもなくこれは君の羽だ。 柔らかくて、軽い、君の翼。 「ひっくっ……ぅっ……」 もうどんな顔で君の前に現れていいのかわからない。 俺が壊してしまった。 俺が森に誘ったのだから。 俺が誘わなければ、君は翼を失うこともなかったのに。 君と過ごしたあの日々は、きっともう戻らない。 |