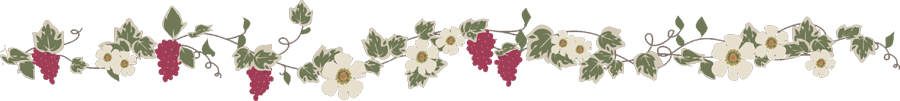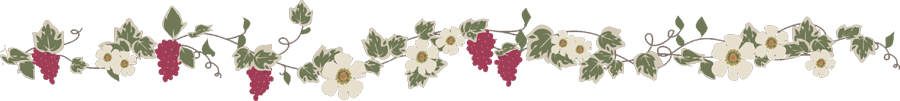

■Angelsyndrome×悪魔症候群■ハロウィン■サリエル×ゼルク(サリエル+バラキエル)■ ※「Angelsyndrome」サリエル×ゼルク前提のお話。 サリエルが他の天使に少々手を出してます。 サリエル視点。 いつものように森へと向かい、使い魔を放す。 遊びに出掛ける使い魔の背を見送り付近を歩いていると、すぐさま異様な光景が目に入った。 ああ、これは関わらない方がいい。 そう思う俺の気持ちとは裏腹に、相手も俺を見つけてしまう。 「あ、サリエルだ」 名前を呼ばれたら、さすがにスルー出来ない。 「はいはい。なぁにやってんだ、お前は」 頭には悪魔の角。 背には悪魔の羽。 ……けれども、こいつが天使なのを俺はよく知っている。 「バラキエル」 「今日はハロウィンでしょ」 それで、悪魔のコスプレをしているということだろう。 最も、ここじゃ普段から悪魔なんてゴロゴロいるけれど。 「サリエル、知ってる? ハロウィンはオバケが来る日なんだよ」 「そうだな」 「仲間と思わせて、イタズラされないためにオバケの格好するわけだろ。俺は、悪魔に仲間と思われたいからこの格好にしたってわけ」 「お前、普段から悪魔ぶってんだろ」 バラキエルの背に生える翼は、本来真っ白の物。 それをこいつはいつも黒く染めていた。 悪魔の羽と似たものになるように。 「今日はより一層悪魔になってみてんだよ。角とか」 まあ普段からここまでしてたら、さすがに叩かれかねないだろう。 こいつの悪魔好きは異常だと感じる。 もうこの場所で、異常とか正常とか考えることもバカらしいけれど。 「似合ってるよ」 「ありがとう」 「じゃあ、俺はもう行くから。悪魔に遊んで貰えるといいな」 適当に話を終わらせようとするが、バラキエルは俺の服をぎゅっと掴む。 「元々のハロウィンの由来とか、どうでもいいからさぁ。サリエル。トリックオアトリート」 振り向くと、バラキエルはペロリと舌なめずりをする。 しょうがなく、俺はポケットからお菓子を取りだした。 「ほら。菓子」 「えー、なんでお菓子持ってんだよ」 「想定外?」 「普通、持ってないからねぇ」 「そんなに俺にイタズラしたかったのかよ。残念だったな」 バラキエルはうーんと悩む素振りを見せ、俺の手を取り、ポケットに菓子をしまわせる。 「サリエル。俺に、お菓子かイタズラか選ばせて?」 やっぱり、めんどくさい提案だ。 「はぁ……」 俺は小さくため息を吐く。 「ねぇ、お菓子いらないから、俺にイタズラしてよ」 「違わねぇ? 普通、菓子無かったら俺がイタズラされるんだろ」 「普通とか、考えるだけ無駄だってわかってるくせに」 地面へと座り込み、長い前髪の隙間から俺をじっと見上げる。 本気の目だ。 普段、見せてないだけに、その視線に捉われると、なんだか逃げづらい。 俺は、そっとバラキエルの髪に触れる。 やわらかくて、ふわふわしていて。 元々は白に近い綺麗なクリーム色。 なんでわざわざ黒にするんだとか、俺が口出すことじゃないけれど、少し惜しいような気がしてしまう。 「……後で泣くなよ」 俺は剣を抜き、バラキエルの髪を少しだけ切り落とす。 「あ……」 「隠すなよ」 こいつは目でものを語る。 目を隠して、心を隠す。 俺はしゃがみこみ、バラキエルと視線を合わせた。 「翼出せ」 「……なんで」 「いいから。出せって」 強めに言うと、バラキエルはしぶしぶその背に翼を広げる。 本物の、天使の翼だ。 やっぱり中途半端に黒に染めてはいるものの、白い部分は残っていた。 そこから1本、長めの羽を抜き取る。 「っ……なに?」 俺が少し体を離すとすぐさまバラキエルはもう一度、翼を隠した。 「綺麗な白だよなぁ。バラキエルの羽」 わかりやすくバラキエルの表情が歪む。 いつもなら隠せていた瞳が、不快の色を示す。 「誘ったのはバラキエルだろ」 「……そうだけどぉ」 「刺したり踏んだり、望まれるがままの苛め方するとでも思った?」 服を裂き胸元を晒させる。 バラキエルが大嫌いな白い羽で肌を撫でてやると、逃げるよう体を震わせた。 「んっ……こういうの、やだ」 「わかってる」 乳首を柔らかい毛で何度もくすぐっていく。 いくらそれが嫌いな羽であったとしても、エロいことが大好きなバラキエルの体は、徐々に熱を帯びていった。 「完全に勃起してんな。こっちも、この羽で撫でてやろうか」 「手でしてよ」 俺は、バラキエルの言い分を無視し、羽で先端を蜜を拭う。 「ぁ……ん、んっ」 「すごいな。どんどん溢れて来やがる」 腰が浮きはじめ、バラキエルがすがるよう俺の腕を掴んだ。 「ん、じれったい」 「わかってる」 「やだ……はやく……」 「別に、俺はお前を甘やかしたいわけじゃねぇしな」 「サリエル……」 「俺もお前の嫌いな天使だし」 「っ……そうだけど」 心を読ませたくないのか、バラキエルは目を伏せる。 俺は、羽の根本をバラキエルの鈴口にあて、ゆっくり押し込んだ。 「あっ……ぁっ……んぅっ」 「自分の羽、感じる?」 バラキエルは首を横に振るが、感じているのは明らかで、ビクビクと体を震わせ、背中から翼を出す。 「あっ……はぁっ!」 「翼、もう隠せねぇの?」 たぶん、普段のこいつならセックスしてでも隠せるだろう。 それくらい、なぜだか今は感情が昂っているようだ。 「サリエルっ……ん、ん、それ……やだっ」 「知ってる」 バラキエルが大嫌いな自分の羽。 その羽で、気持ちよくなるだなんて、不愉快極まりないだろう。 尿道の中、奥へと羽を差し込んで、掻き回すとぐちゅぐちゅいやらしい音が響く。 「やっ……んっ……んっ!」 「いきそう?」 「はぁ、やっ……んーっ! んぅん!」 バラキエルの体が大きく跳ね上がり、羽の隙間からどぷりと白濁の液が漏れて来た。 「ふっ。天使の羽、大好きだな」 「っ……違うよ」 「こんなに早くイっちゃったのに?」 「ん……尿道が好きなだけで、羽が好きなんじゃない」 さすがに小さく笑ってしまう。 俺は手を伸ばしバラキエルの背中の翼を撫でてやった。 「んっ……んぅ」 「気持ちいいくせに」 「よくない。いらないよ……こんな羽」 「それは言うな」 「ん…………」 「お前が悪魔を好きで、天使を嫌ってもいいから。この翼は残しとけ」 バラキエルが、微かに頷いたように見えた。 「よし」 「……頭のいい天使は嫌いじゃないよ」 「お前より頭のいいやつなんて、そうそういねぇよ」 俺は、入ったままだった天使の羽をバラキエルから抜いてやる。 「悪いな。バラキエル。そろそろ行くわ」 「やっぱり」 「……やっぱり?」 「俺のことは、刺してくれないんだなぁって」 バラキエルは、立ち上がる俺を見上げにやりと笑う。 まるでこうなることがわかっていたように。 「間違って欲情したら困るだろ」 「すればいいよ」 「……お前だって、本当は悪魔に犯されたいくせに」 「でも、こんな風に髪切られちゃったらさぁ、他の人とセックス出来ないよ」 「出来るだろ。なんなら後ろから犯して貰えよ」 ひらひらと手を振り、バラキエルと別れる。 夜が更けるころには、悪魔が通りがかるだろう。 そんなことを思いながら、俺は自分の部屋へと戻った。 「あ、サリエル。おかえり」 「…………ゼルク?」 誰もいないと思っていた自分の部屋には、なぜかゼルクがいて俺は一瞬言葉を失う。 「なんだ。今日はネルと遊ぶんじゃなかったのか?」 「遊んだよ。もう遊び終った。夜は……ここに泊まってもいいだろ」 恥ずかしいのか、ゼルクの目が泳ぐ。 「まあいいけど。なに? 珍しいな」 「だって、今日はその……ハロウィンだし」 「ああ、苛められに来たのか?」 「ち、違う。菓子貰いに来ただけ」 「はいはい」 菓子貰いに来ただけで、泊まるってのはどういうつもりなのか。 ここはあえて突っ込まないでおく。 「ホントだからな。俺は菓子ないけど、サリエルがくれる係だし」 俺はゼルクの腕を引き、後ろからその体を抱きしめベッドに腰かける。 「苛めていい?」 「ダメだって。なに聞いてんだよ。サリエルは菓子くれる側だっつってんだろ」 「じゃ、少しだけ刺していい?」 「それもダメ……ん、んぅっ! 人の話聞けよ」 俺はゼルクの言葉を無視し、手にしたナイフで胸元に線を引く。 「もうっ!」 バタバタと暴れるゼルクを片腕で抱き、首筋に顔を埋め、軽く噛みついてやる。 「いっ……ぅうっ」 「溜まってんだよなぁ、誰か苛めたくてしょうがねぇ気分なんだよ」 「っ……誰でもいいのかよ」 「誰でもいいわけないだろ」 少しだけゼルクの暴れる力が緩む。 その隙に、ナイフの先を押し入れ軽く掻き回すと、どぷりと温かいゼルクの血が溢れ、俺の手に絡みついた。 「うっ……やだ……あっ」 「そろそろ慣れろよ。すっげぇ音」 「あっ……音、立てんなってっ。んーっ」 「力入れると、余計溢れんぞ?」 「やっ。はぁ……サリエルこそ、そろそろ飽きろよ」 「飽きるわけねぇだろ」 ナイフを引き抜いて、代わりに指を刺し込んでいく。 ゼルクの体内が温かくうねりながら、ビクビクと脈打ってくれた。 「しよっか、ゼルク」 「なんで、この状態で欲情出来んだよっ」 「ゼルクだって、もう熱くなってんだろ」 空いた手をズボンの中へと差し込む。 ゼルクのソコもまた熱を孕み、背に生やした翼はビクビクと震えている。 「あっ……ん、んぅ」 「この状況で、よくすぐ勃起出来るよなぁ?」 「うぅっ……あっ、サリエルのせいだしっ」 「俺のせいじゃなきゃ、嫉妬するとこだった」 熱いゼルクの体液を纏った手で、音を立てながら熱を煽っていく。 「はぁっ、あっ……んぅ……」 「……やる気出て来た?」 「っ……ん。後で、ちゃんと菓子くれるんだろうな」 「ちゃんとやるよ」 「絶対だからな」 「先に、イタズラな?」 「っ……今日だけだからな。今日は、ちょっとくらい、許してやる……っ」 「はいはい」 いつまでも、喚き続けそうなゼルクの唇を、そっと俺は自分の口で塞いだ。 |